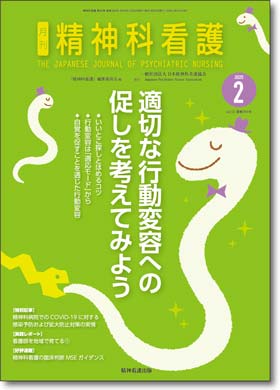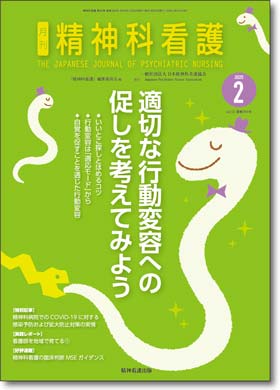「なんであんなことするんだろうな……」「あの行動,変わってくれないかな……」そんなモヤモヤとイライラを抱えながら患者さんや利用者さん(あるいは身内)に接していませんか? そして,「よし,変えさせよう!」とアレコレ注意したり,アドバイスをしてはいませんか? どうでしょうか? それでその行動は変わりましたでしょうか? 変わるどころかヒドくなっているかもしれません。「変わってほしい」という気持ちは痛いほどわかりますが,はやる気持ちはおさえて,支援は急がば回れ,ご本人がおのずから変わる支援をめざしてみませんか? 今回の特集はそんな企画です。
まず冒頭記事では,ご存じ土屋徹さんに「いいとこ探しとほめるコツ」と題して,SSTの基本と応用,ご本人の意に沿わないような方法ではない,自然と好ましい行動を増やしていくような行動変容のための支援の枠組みについてご紹介いただいています。座談会①ではリカバリーをめざす認知療法(CT-R:Recovery-Oriented Cognitive Therapy)にもとづく,「患者モード」から「適応モード」を増やしていくことでの行動変容のありようについて解説していただきました。そして座談会②では児童・思春期病棟の実践から,「変える」のではなく,本人の自覚を促し,おのずから変化していけるようなかかわりや,コミュニケーションのコツについて検討していただきました。