|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
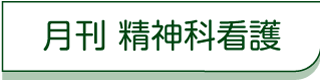 |
 |
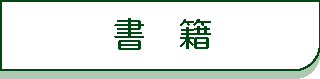 |
 |
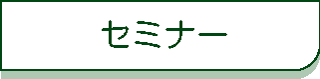 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
10月9日(土)、小社主催の『水中毒・多飲症患者へのケアの展開』東京セミナーを、総評会館にて開催しました。小雨の降る中、48人の看護師さんにご参加いただきました。
午前中は神奈川県立保健福祉大学の吉浜文洋先生に講義していただきました。水中毒・多飲症のケアにあたって基本的な考え方や配慮すべきこと、また看護者が陥りがちな悪循環から抜け出し、信頼関係構築するポイントについて、裁判事例などもふれながらわかりやすくご解説いただきました。
午後は、松原病院の篠川悟看護師に、病院におけるケアについて具体的にご報告いただきました。多飲症の患者さんを退院に結び付けていくまでの粘り強い取り組みが活き活きと伝わってきました。
質疑の時間は、参加者から多くの質問や意見、事例やケアの工夫などが出されました。たとえば「隔離解除するとすぐ蛇口に向かってしまう患者さんに、どのようなかかわりをしたらよいのか」「飲水してもらうコップの大きさはどのぐらいのものにしたらよいのか」などの質問、また「飲んだ量を紙に記入してもらい自己申告する取り組みが有効だった」「外出してレストランに行ったときは、院内にいる時のようなこだわりはなくなっている」など、ケアの工夫や発見などなど……。あっという間に終了時間となってしまいました。
参加者のみなさんには好評をいただきました。以下、感想を紹介します。
|
|
|
 |
|
多飲症患者への対応の仕方の参考になった。他病院での取り組みや悩みが多く聞け、「これから再び考え看護していこう」というモチベーションにつながった。
|
| |
多飲症に対する関わりの打開策のヒントをもらったように思った。今、病棟で悩み「やってみよう」と思っていることがあるので、やっぱり「やらなきゃ」と思っている。
|
| |
講義を受けたことで、自分たちの行っているケアを修正しないといけないことに気づいた。慢性期の水中毒・多飲症患者を対応している。その方に対して、水の管理、定期wet測定をしており、どこかで満足、十分なケアを提供していたと思っていた。どこからできるかわからないが、まず自分自身をもう一度見直し、スタッフ一丸となって患者を内面的にケアしていかなくてはいけないと思った。
|
| |
制限看護が悪循環となっていることを聞き考えさせられた。軽い意識障害がでてからどうするか考えてもよいのではという話には、スタッフのピリピリした態度が患者にストレスを与えていると思った。飲水している観察情報が大事で、意識障害がおきた時に処置を考えればよいのではないかと思う。
|
|
一方で、「グループワークを行ったほうが多くの意見が出てよかったのではないか」「科学的な根拠が得られなかったのが残念」という厳しいご意見もいただきました。次回より、改善していきたいと考えております。
講師や参加者のみなさんのお話をお伺いし、みなさんのケアにおける柔軟な発想や、試行錯誤しながら粘り強く取り組んでいることを知り、頭が下がる思いでした。マニュアル通りに進まない多飲症看護は本当に大変だと思いますが、だからこそ、看護って面白いし、みなさんの力が発揮されるのだと痛感しました。こうしたみなさんの力を次の企画に結び付けていきたいと思います。みなさん、本当にありがとうございました。
それから、会場の冷房が強くて、体調を崩してしまった参加者の方がいらっしゃいました。申し訳ありませんでした。社員一同、回復をお祈りしております。
|
| |

|
| |

午前の講義(吉浜先生)
|

病院でのケアの報告(篠川看護師)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |