|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
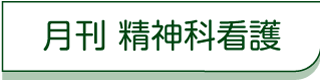 |
 |
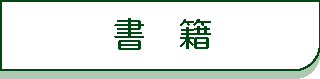 |
 |
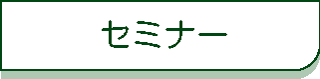 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
月刊誌『精神科看護』2010年4月号より連載開始となった「ケア百物語」。このコーナーは臨床で出会う患者さんとの「ちょっと困ってしまった」場面を、機知に富んだかかわりによって"少しだけ前進させた"体験談を紹介していただくというものです。
「Web版ケア百物語」では、雑誌に掲載された体験談を再載するとともに、みなさまのケア百物語を募集します。お送りいただいた原稿については、編集部で一部編集のうえ、投稿者への確認を経て、Webにて紹介させていただきます。投稿は下記の投稿フォームをご利用ください。
|
| |
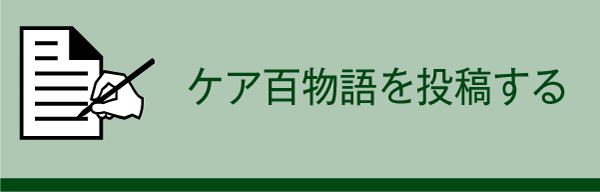
|
|
|
| |
第36話 「さだまさしが好きです」
|
| |
私が精神科に勤務して1年が過ぎたころに入院してきた50代の女性患者,Aさん。ADLは自立していて入院前は1人暮らしをしていた。企業の障がい者枠で働いていた。しかし,IT化の流れについていけずストレスが増大していき,幻聴・体感幻覚・不眠が顕著となって当院に入院となった。
またAさんには出産時の後遺症による脳性マヒにより緊張性アテトーゼがあり,動作困難が見られていた。動作がゆっくりで,発音も聴きとりにくい状態であった。プライマリーとなった私は,当初,一語一語を区切ってゆっくりと話すAさんの話が解りづらく,会話によるコミュニケーションがうまくいかないと感じ苦手意識をもっていた。「食事は摂れたのか」「便は出ているか」「入浴できているか」などの情報は取れるものの,「復職に向けてどのように考えているか」などの話になると,Aさんは緊張が強くなり,顔をこわばらせてしまう。Aさんが何を考えているのかわからず,私自身が不安を覚えていた。
そんなある日,Aさんのことをどうすれば少しでも理解できるのか,どのように声かけしたらよいのか,とあれこれ考えながらベットサイドに行ったときのことだった。ふと思いついて「好きなタレントはいますか?」と,訊いてみた。するとAさんは,「さだまさしが好きです」と話してくれた。私が「いいですよね。歌もいいし,話も面白いですよね」と返すと,うれしそうに笑顔を見せてくれた。それから数日後,ベットサイドに行った際,“さだまさし”のCDとプレーヤーが置いてあることに私が気づくと,「時々,聴いています」と笑顔で話してくれた。それから,曲と出会ったきっかけはなんだったのか,コンサートに行ったときの話などしてくれた。友人がCDを貸してくれたことがきっかけで曲が好きになり,毎日聴くようになったのだそうだ。歌詞がよく,聴くと癒されるのだとAさんは笑顔を見せて話してくれた。
“さだまさし”でつながって以来,Aさんは訪室時に私の顔を見ると笑顔を見せてくれることが多くなり,さだまさしの歌のように,語りかけるかのように復職に対する思いをポツリポツリと話してくれるようになった。Aさんは就職してから都内のワンルームマンションをローンで購入していたのだが,プライマリーだった私は,退院前訪問でPSWとともに当のマンションに行ったことがあった。部屋の片隅には“さだまさし”のCDが積んであった。閑静な住宅地の中,そのマンションはけっして大きくはなかったが,Aさんの家は最上階の角にあった。復職に最後までこだわりを見せていたAさんは,「また,家で暮らしたい」と私に語った。そのため担当医から復職は難しいのでは,と現実を告げられたとき,全身に力を入れて身体を震わせていた。復職ができなければ,自分の家を手放さなければならないことになると感じていたのだと思う。それ以来,話が今後のことに及ぶと口を噛みしめて全身に力が入った。
残念ながらAさんは,希望していたナイトホスピタルでの復職はできず,精神状態が悪化し重度障害者施設に入所となってしまった。入院時は「適応障害」と書かれていたが,遅発性の統合失調症の診断へと変わっていき,実家近くで療養することとなったからである。
私はAさんとの出会いを通して,2つのことを感じた。1つは,障害があって話し方がぎこちないAさんに対し,偏見をもっていたのは私自身だっということに後から気づいたこと。私自身まだ看護師経験が浅く,2つの障害が併存するケースでは対応が難しいと勝手に思い込んでいたのだが,不安感や緊張感は相手に伝わるものだ。Aさんもはじめて出会う医療スタッフに不安と緊張を覚えていたのかもしれない。しかし一方で,ケアする者の気持ちが変われば相手の気持ちも変わっていくことを,Aさんは身をもって教えてくれた。自分の中にある思い込みを疑い,目を向けていくことの必要性を考えさせられた。そして,人と人とのつながり,心と心の交流を大切にしたケアをしていきたいと思ったのだった。
2つ目は,「好きなこと」を支持していくことそのものがケアにつながっていくこと。このエピソードをきっかけに,ほかの患者さんにおいても趣味や好きなことをケアに活かしたいと考え,カルテを読み直した。患者情報用紙の趣味趣向欄には囲碁,将棋,旅行,映画鑑賞,などと書かれている。中には空欄のカルテもあった。入院時は優先順位が低い情報とみなされたのかもしれない。しかし,あれ以来私は,この部分にも注目し積極的に情報を取るようにしている。
Aさんは,今日も“さだまさし”を聴いているだろうか。
(東京都・公益財団法人神経研究所附属晴和病院・増田 忠)
|
| |
|
|
第35話 「このおっさんもイライラします?」
|
| |
日ごろ患者さんとかかわっていると,たまに人間同士の距離感について考えることがあります。それは,単に“ていねいにかかわることが大事だ”(もちろん,基本的なとても大切なことですが)という意味に留まりません。それはもっと原理的な「人間と人間の距離が近くなるということはどういうことなのか」というような問いです。こうしたことを改めて考えることが増えました。
特に長期入院の患者さんとのかかわりにおいては,そのことを強く意識します。長期入院の患者さんとは,いろいろな意味で,長い付きあいになってしまいます。表面上の関係性は,「患者さんと看護師」としての付きあいですが,期間が長くなればなるほど,どうしても“慣れ”というものが生じてきます。プロの看護師として,一定の距離感を保つということが必要なのもわかっています。しかし,人間対人間である以上,良くも悪くも“慣れ”というものが生じることは避けられません。
“慣れ”の度合は相手の特徴や自分との関係性によって程度の差があるのはわかっていますし,同時に,行き過ぎた“慣れ”は患者さんとの関係性の発展や治療の妨げになる可能性があるというのも,理解しています。“慣れ”によって,さまざまな局面で判断が鈍り,患者さんを悪い方向に導いてはなりません。これは何も患者さんに対してだけではなく,仕事を離れた私たちの普段の生活の中での人間同士でも,同じようなことが言えるのだと思います。
このように看護において(あるいは一般的に),“慣れ”は悪いものととらえられがちですが,一方で,患者さんと看護者関係の“慣れ”をケアに活かすことができないだろうか,“慣れ”を看護に活かせるかどうかが,看護師の手腕ではないか,と思うこともあります。
私自身と患者さんの“慣れ”が,治療や看護において良好な結果を導いたであろう一場面を紹介します。
★
ある日,患者さんが何かに対して苛立ちを覚えて,ナースステーションに来られたときの話です。
「あのおっさん,イライラするわ。頓服ちょうだい!」。
その患者さんは,ものすごい剣幕で話されていました。このとき私は自分自身を指して,「このおっさんもイライラします?(ここで言うおっさんは私のこと)」と言うと,その瞬間,患者さんは「はははははー」と笑顔になりました。
当然,患者さんの訴えを真剣に聞くという方法もあったのでしょうが,私はこの方に,こうした方法をとりました。一見「ふざけているだけ」のように感じられるかもしれません。私とこの患者さんとの関係の中に,“慣れ”があったことも事実でしょう。でも,それは“慣れ”という名の信頼関係が基礎にある,という前提で選択したコミュニケーション方法でした。
もちろん,判断を間違えば,つまり,そうしてはいけない状況でこうしたコミュニケーション方法を選択してしまえば,患者さんは不快に思うでしょうし,状況によっては,精神状態の悪化にまで影響することがあったのかもしれません。ただ,患者さんとのかかわりで,よりリスクの低い,かつ有効なかかわりを瞬時に選択する必要があるという視点で考えてみても,このときの患者さんとのかかわり方は,私の判断の中では決して間違っていなかったと思うのです。
判断の基準となるのは,この患者さんが本当にいま,頓服薬や薬の増量が必要なのかどうかです。私たちは,まず薬を飲んでもらってから次のアセスメントをしようとします。しかしそれでは,看護の本質が見えなくなります。薬が万能であれば積極的に飲んでもらうべきですが,どんな薬にも必ず副作用がありますから,患者さんの苦痛を最小限に抑えるためにも,それまでにできる看護を考えることが“看護力”ではないでしょうか。
また,薬以外で患者さんとのかかわりを見出すとき,看護者も自分の特色を出していいと思うのです。たとえ,よくスベる私であっても,その患者さんにはウケると思えば,笑いを提供するのも看護だと思いますし,それを選択するのも看護判断だと思うのです。
人は,かかわることで脳細胞が活性化し,ネットワークが構築されます。これは,脳が委縮していようが,身心に障害があろうが,リハビリをすることにより,可能な限り回復しようとします。この力は,場合によっては,薬以上の効果をもたらすことがあることは,臨床で実感しているところです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉は,常に意識しておかなければなりませんが,完全な他人行儀に接するという「礼儀」だけでは解決できないこともあると思います。
ここで紹介したエピソードは,患者さんが薬を希望しているときに結果的に薬が要らなかったという話をしていますが,そこに至るまでに私たち看護師は常に患者さんとかかわっているわけですから,日ごろのかかわりがいかに重要かということを改めて考えさせられます。
こんな細かい話をしていますが,実際は脳細胞とか脳の委縮だとか,そんな詳細な理屈を考えながら患者さんとかかわっているわけではありません。そう考えると,看護師のコミュニケーションは,教科書の基本では説明しきれない一瞬一瞬の判断と人間らしさが求められる職業かもしれないと思うわけです。
私たち看護師には,患者さんの尊厳を保ちつつ,可能な限り安らぎを提供するということが求められます。そのなかで,患者さんに対して,より自然な環境を提供するために,看護師自身もいかに自然に振る舞えるか。近ごろは,そのようなことを考えることに看護の奥深さと楽しさを実感しています。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第34話 「ブタ!? 違いますよ,ウサギです。見えませんか?」
|
|
私が勤めている病院は,横浜の中でもとても緑の多いところです。その病院の3階,男性閉鎖病棟でのある患者さんとの出会いをお話したいと思います。
その患者さんは躁状態で気分変動が激しく,保護室に入っていらっしゃいました。対応するたびに大声をあげられ,拒否的な態度を示すその患者さんには,職員もかかわりに困ってしまうことがたびたびで「もう,やんなっちゃうわ」とステーションの中でため息が出てしまうような状況でした。
ある日私がその方のところに行ったとき,「誰だ? あんた」と聞かれて名札を見せようと近づいたときのことです。
「あー見えた見えた! ブタがいるわ!」。
―その言葉は少しだけ小さなマツコ・デラックス体型の私に向かって発せられた言葉でした。そのとき私は「ブタ!? 違いますよ,ウサギです。見えませんか? ほらながーい耳が付いてるでしょう?」とウサギに似せたジェスチャーを交えて返しました。私はもともと,冗談まじりの受け答えが苦手なほうではありませんが,保護室に入っているような患者さんには何かを言われても黙って受け流すことが多く,このような対応はしたことがありませんでした。しかし,今回はなぜか,咄嗟にこのような言葉を切り返してしまいました。患者さんは目をこすり,私を二度見した後で「……耳? ウサギ? 見えねえよ……」と戸惑っておられましたが,私は「落ち着いたら見えるようになりますよ」と伝えて退室しました。そのやりとりは私が患者さんにかかわるたびに何回かくり返されましたが,大声をあげることも拒否されることもなく,むしろそのやりとりを楽しんでくれているようにも感じられました。
次第に患者さんは「ウサギちゃん」と冗談まじりに私を呼ぶようになり,まわりの職員はなぜ私がウサギに見えるのか疑問が膨らむなか,患者さんが受け入れてくれる職員の1人になれました。ぶっきらぼうだった言葉が少しだけ柔らかくなり,日常会話やふてくされながらも冗談が聞けるようになったり,拒否が強いときの交渉役になることもありました。
躁状態で,すべての人に怒りをぶつけていた患者さんにとって私のとった対応は想像と違う,意表をついたものだったかもしれません。患者さんから受けた言葉を冗談のように受け取り,切り返したことで,この方の怒りをなくし受け入れてもらえたのは,精神科看護としての正しい対応とは言えないかもしれません。ただ,その後の治療がスムーズに進んだという意味では,1つの対応として成功したのではないかと感じています。
しばらくして患者さんの状態も落ち着き,大部屋に移ったころには「ウサギちゃん」ではなく,私の苗字である「山崎さん」に変わっていきました。
その患者さんは「前にブタって言って悪かったね」という言葉を残して退院していかれましたが,私はこの患者さんとのかかわりの中で状態の悪い患者さんから発せられた言葉に巻き込まれない対応の仕方を学んだ気がします。症状にとらわれ苦しんでいる患者さんには,私たち看護師が味方ではなく,敵のように感じることもあるかもしれません。そんなときに発せられるストレートな言葉をこちらが感情的に受け止めず,聞き流したり,うまく交わすことができたなら,看護師としてもう一歩患者さんの気持ちに寄り添うことができるのではないかと考えます。切り返しと少しのユーモアが患者さんと看護師の関係をよい方向に導いてくれる,これは精神科看護には必要な力かもしれません。
私の対応がすべての状況や症例に対して適切なものであるとは言えませんが,患者さんの言動に揺さぶられずかかわっていける力を,今後も身につけていけるよう努力していきたいと感じさせられる事例でした。
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第33話 「いいよね,人間らしくて」
|
| |
私は他施設でICUに勤務した後,当院(開放病棟のみの精神科病院)に入職しました。いまから2年半前のことです。初めての精神科。ICUでは業務に追われ息をつく間もなかったのに,ここではなんと……やることがない! 病棟の患者さんは自分のことはほとんど自立して行えます。体を動かして何かしていれば患者さんの役に立てていると思っていた当時の私は,ここでは何をすれば患者さんの役に立てるのか,見当がつきませんでした。戸惑いと無力感につぶれそうな日々。先輩に不安な気持ちを聴いてもらったり,疾患や薬物についての学習をするものの「自分はここにいていいのだろうか……」という思いと日々闘っていました。
そんな私を励ましてくれたのは患者さんとの愛おしい場面です。「道端で死んだ小鳥が切なくて交番に届けた。命って儚い」と目に涙を溜めながら語る患者さん。聴くことしかできなかった私に「一緒に供養してくれてありがとう」。また,洗髪介助をしたら「お礼にあげられるものが何もないから」と,美しいソプラノで『蘇州夜曲』を歌ってくれた患者さんも。そんなとき,私は心から「患者さんが好きだ」と思うのでした。「疾患や症状だけを看るのではない,ここでは患者さんのまるごと全部とかかわるんだ」。そんな実感と感動を何度も味わううちに,私はすっかり精神科看護の世界に引き込まれ,「なんだか面白くなってきた」。そう感じはじめたころのことです。
ある日,うつ病で休職中の入院患者Aさんから「原口さんが生き生きと働く姿を見ると焦る」と言われたのです。私は再び悩んでしまいました。私はここで何をすればよいのだろう。患者さんは何を求めているのだろう。そんな問いに明確な答えをもてないまま入職2年が過ぎたころ,やはりうつ病で休職中の入院患者Bさんが私にこう言いました。「原口さん,何日か休んでたね。いいよね,人間らしくて」。
実際にはBさんの外泊と私の夜勤明け休みがたまたまつながり1週間近く顔を合せなかっただけなのですが,私の中の何かがその「人間らしくて」という言葉に反応しました。「人間らしい?」と返すと,Bさんは「うん,人間だから休むって普通のことだよね,休んでもいいんだよねって思えたよ。楽になった」と話されました。その言葉を聞き,入職以来私の胸の中につかえていたものがすっと落ちた気がしました。
小さいながらも病棟も1つの「社会」です。社会では人は人に学びます。私たちはたまたま「患者」と「看護師」という立場で出会ったけれど,まずは1人の人間同士です。患者さんは患者さんのままに,私は私のままに生きて,その生き様から自然に学びあう視点(ケア)があってもよいのではないか,と気づいたのです。この病棟を舞台に,患者さんが,看護師が,それぞれの“いま”を悩みながら,迷いながら,生きている。与えることばかりを考えていた頭でっかちの新米看護師に患者さんが道を示してくれました。背伸びをせずありのままの自分で,患者さんとともに生きていくことに誠実でありたい。そんな看護観を後押しされた,小さな物語です。
(東京都新宿区・公益財団法人神経研究所附属晴和病院・原口眞理子)
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |