|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
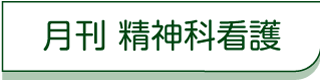 |
 |
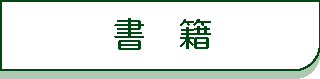 |
 |
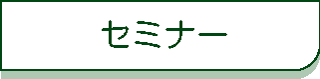 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第17話 居心地のいい存在になろう
|
| |
看護師になって2年目のころ。私が勤務していた閉鎖病棟に,50代の統合失調症の女性患者さん(Aさん)が入院してきました。躁状態で,警察や市役所に苦情の電話をかけまくって,多動で痩せも目立ち休養を必要としていました。医療保護入院に納得されていないAさんは,その日から私たちナースに怒りをぶつけてきました。毎日,ナースステーションのドアにはりつき,「なんで私が入院させられないけんとね!」「男の後ばっかり追いかけて! 淫乱女!」など,若い女性スタッフへの罵声は特に激しく,スタッフも疲弊していました。
あるとき,通りかかった私に,Aさんは「宝塚の男役をしよったろうが!」と大声で怒鳴りました。単純な私はなんだかほめられた気持ちになり,そのことが縁で,私はAさんの受け持ち看護師となりました。「私にできることはなんだろう」「Aさんの不満を軽減するにはどうしたらいいんだろう」。いろいろと考えたものの,当時の私には「話を聴く」ことしか思い浮かびません。Aさんとの,毎日の面接が始まりました。面接ではAさんに「いまは休養が必要」「症状が落ち着けばすぐにでも退院できる」ということを伝えていきました。しかし「あんたに言うてもわからん!」と,Aさんの不満は軽減するどころかますますヒートアップ。そこで原点に戻り,自分の言動を振り返ると,私は自分の思いだけを伝え,Aさんの怒りや悲しみに寄り添えていないことに気づきました。それ以来,私は「Aさんにとって居心地のいい存在になろう」と,共感的にAさんの訴えにかかわっていきました。
しばらくすると,Aさんの怒りもだんだんと収まり,不満言動や暴言も減っていきました。いつしか普通に会話ができるようになり,冗談も言えるようになりました。やがてAさんから「面接,もういいから」と言われ,私との面接は突然に終わりを迎えました。私のほうがかえってさびしく,不全感が残ったような収束でした。
1か月後,私の勤務異動が決まりました。帰ろうとすると突然,Aさんが私のもとに駆け寄ってきて「あんた,おらんごとなると? これから誰に話を聞いてもらうん?」と泣いてくれたのです。私は涙がこぼれ落ちないように我慢しながら,「誰でも聴いてくれるやん」と言葉を返しました。Aさんが私のことをそんなふうに思っていてくれたことがうれしくて,帰りの車の中でも,お風呂でも,号泣でした。
Aさんが穏やかになれたのは,薬が効いてきたからかもしれません。病院という環境に慣れたこともあるでしょう。でも,私とのやりとりも,Aさんの変化に何かしら影響を与えられたのではないか,と思います。人は,話を聴いてもらうことで「大切にされている」「必要な人間である」と感じるといいます。あの面接は,Aさんと看護師の私がお互いの必要性を確認した作業だったのではないかと思っています。
本音をいうと,毎日話を聴くのはしんどかった。でもAさんの最後の言葉は,どんな素晴らしい映画にも勝る感動を与えてくれました。私がいまでも精神科の看護師を続けられているのは,Aさんに出会えたからです。
|
|
|
| |
第16話 本当はね,やれなかったわけじゃなくて,やらなかったの
|
| |
入退院をくり返すたびに家族への依存が強くなっていったAさんは,いつしか自分から歩くのをやめ,他院では車椅子での生活を送っていたようです。
今回の入院も,家族がAさんとの生活に疲弊したため,互いに距離をとって休養することが目的でした。入院直後のAさんは「何もできなくなっちゃったの」と意気消沈し,自室中心の生活を送っていました。日常生活の中から,少しでもできることをやってみようと勧めても「できない」「いまはできないって言っているのに」と,看護介入を連日拒否しては過呼吸をくり返し,そのたびにナースコールが続きました。Aさんとのつきあいが長く,担当看護師である私は,いつも同じ態度で接し,この時期も,しばらく見守る姿勢を続けました。Aさんが具体的に思いを言語表出したときには,十分に話を聴きました。そのうち,少しずつ,Aさんのペースで入浴などができるようになっていきました。
しかし,Aさんは唯一「手が届かない」「痛いから」と1日2回,同じ時刻に,腰部への湿布貼付を求めてきました。はじめは単に「手が届かないから仕方がないか」と,介助することに疑問をもつことはありませんでした。しかし「今日はこのあたりに貼ってほしい」とAさんは手を腰部にのばして,湿布場所を指定してくるようになったのです。このころのAさんに過呼吸はみられず,家族と外出するまでになっていました。日中の会話も,退院後の自宅生活の内容が中心でした。
あるとき,Aさんは「湿布は同じ時間に貼り替えると調子がいい」「後は腰痛がよくなるだけ」と言いました。その言葉から,担当看護師として,Aさんはこれ以上退行しないと判断し,しばらく看護計画の中で介助していくことを共有しました。ほかのスタッフからは「依存性があるのではないか」と不満の声もあがりましたが,私はAさんを信じていました。
やがて,自然とAさんからは湿布の希望が聞かれなくなりました。退院日時を決める少し前,さり気なくAさんにその理由を尋ねました。すると,Aさんは「もう必要ないの。やってもらってずいぶん経つし。本当はね,やれなかったわけじゃなくて,やらなかったの。家に帰ったらやってもらえないしね」とハニカミながら言ったのです。
湿布の貼付を通して交わされていた二言三言の会話から,Aさんの心境がどのように変化していったのか。その疑問が解けたのは,湿布の介助がなくてもそばにいる看護師との空間に,満足気な表情を浮かべるAさんを見たときでした。きっと,自分をまるごと受け入れてくれる看護師の存在が“人生,そんなに捨てたもんじゃないな”“いつまでもこんなことをしていられない”と,Aさんの気持ちを動かしたのではないかと思いました。
他愛もない看護かもしれませんが,Aさんとのかかわりの積み重ねから,患者のニードに隠された思いを汲みとりながらかかわっていく必要性を学びました。同時に看護を通して,Aさんの皮膚に自我が宿った瞬間をみることができました。
|
| |
|
|
|
| |
思い切って,言葉にして伝えることの大切さを教えられた話です。
それは,統合失調症の患者さん(Aさん)でした。Aさんはいつも,何か言おうとしても「う~ん……」と考え込むばかりで,言おうとしている何かを「いや……」と自分で打ち消していました。手を動かし,何かを伝えようとしているものの言葉にすることができず,誰にもその思いを口にされませんでした。その様子を見て私は,口にしようとして飲み込んだその言葉の中に,Aさんが本当に言いたい思いや聞いてほしいという言葉があると思いました。
私はいつしか,Aさんが口にした後の周囲の反応や「自分の考えが違っていたらどうしよう」と考えすぎているのではないか,また認知の歪みのようなものをもっていて,余計に自分を追い込んで,悩み,苦しんでいるのではないかと思うようになりました。私自身にも,言いたいことを無理やり自分の中に閉じ込めるクセがあります。Aさんの中に,私が私自身をみたのかもしれません。
ある日,Aさんが医師の診察を受けていました。Aさんは医師を前にしていつものように考え込んでしまい,不眠の原因や抱えている思いを言えずにいました。
私はAさんに「夜,1日を終えて,ほかの方が言われたことを“ああいう意味ではないか”“こういうことじゃないか”と考えては“いや違う”と思ってみたり,ほかの方から言われたことを思い出されてはその意味を深く考えて,そんな自分を否定したりしていませんか? 1日1日がとてもつらくて,そんな自分を責めていませんか? そうやって,なんとか毎日を過ごしているのではないですか?」と,思い切って話しました。しかも,医師の診察中にもかかわらず。
Aさんは「なんでわかるの? 心を見透かされているみたい」と驚いていました。一瞬,こんなことを言ってよかったのだろうかと思いましたが,その後Aさんは私やほかの女性スタッフが夜勤をしているときに「○○と考えて眠れないんです」「私は▲▲と思っているんだけれど,おかしい?」など,つらい思いを話されるようになりました。徐々に笑顔も見られるようになり,不眠も少なくなっていきました。
これはその場にいたスタッフもきっと覚えていないような,小さな話かもしれません。でも私はAさんに,相手を非難しないことならば自分の思いを言葉にしてよいのだということ,自分の思いを人に伝えることはとても難しく,でも伝えられたときの喜びはとても大きく,そして自分の心の負担を軽くするのだ,という大切なことを教えてもらったと思っています。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私は以前,自分の看護についての振り返りをかねて患者さんに,看護師のどのような援助が入院中のよい体験になったか,インタビューしたことがありました。その際,どの患者さんからも,ある看護師(Aさん)から受けた援助がよかったとの話が出ました。Aさんは,どこの病院にもいそうな「陽気なおばちゃん看護師さん」でした。Aさんのケアについて,一部ご紹介します。
たとえば,あるうつ病の患者さんは「Aさんは頼んでもないのに,ゴミを捨ててくれたりお茶を淹れてくれたり,いろいろなことをやってくれた。けどそれがありがたかった」と話していました。また,頓服薬を飲んでも頭痛のとれなかった患者さんは「“ちょっとベッドを起こしてみたら?”と,少しだけベッドを上げてくれたんです。すると,その晩から少しずつ痛みが和らいだんです。Aさんのおかげで楽になったなぁ」と話してくれました。また,薬の副作用に悩む患者さんは「副作用で気持ちが悪くなったとき,Aさんが頼んでもないのにあわてて小さな氷を持ってきてくれて“楽になるかわからんけど,口に含んで(舐めて)みたら?”って。ホントに楽になりました。それで,次は違う看護師さんに頼んだら,大きな氷を持ってきてね。口があんぐりしたね」と話してくれました。
このインタビューを聞いていて,Aさんのギャッジアップや氷片といったケアは,症状の根拠はなくとも,患者さんにとっては「自分のことをわかってくれて,そのニードにそっていまできる精一杯のケアをしてくれた」という体験につながっているのだろうな,だから患者さんにとってAさんは「安心できる人」だったのだろうな,と思いました。
一方,ほかの看護師は患者さんにとって「自分を評価する人」であって,安心できる存在ではなかったのだろうな,きっと私も,そうやって気づかないうちに患者さんを評価していたのだろうな,とハッとしてしまいました。
すべてのインタビューを終えたとき,私はトラベルビーの『人間対人間の看護』(1974)の冒頭の詩“わたしにおきていることを,あなたにも,大事な問題にしてください”という一節を思い出しました。いくら知識や教養があっても,どんなに手際のいい援助ができたとしても,相手を思いやる心,相手に関心を向ける看護師の態度がないと患者さんには何1つ響かない援助になってしまうなぁ,と。いまさらながら,私に人を援助することの本質を見つめ直す機会を与えてくれたインタビューでした。
そして最近,デイケアに来ている患者さんから「病棟にいたときよりも,何か雰囲気が変わった気がする。いまのほうがいいな。そう,Aさんみたいな感じかな」との発言が! 私もちょっとは,Aさんのような看護師に成長できたのかな? とうれしく感じた瞬間でした。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第13話 「なんで私のところに来るの?」
|
| |
数年前の出来事です。Aさんは入院したときから黒いダウンジャケットを頭からすっぽりとかぶり,暖かい部屋にもかかわらずまったく脱ごうとせず,しかもずっと壁のほうを向いて顔を見せてくれませんでした。
食事もスタッフが見ている間は食べず,言葉をかけても無反応。もちろん入浴や清潔ケアなども拒否。少しでも触れようものなら「イヤー! 助けてー!」と大声を出されました。それが看護師だけでなく主治医にも同じ反応で,スタッフ一同どうしようかと悩んでいました。
それは私が精神科認定看護師の試験のためしばらく休んだ後の,久しぶりの出勤のときだったと思います。Aさんについて「いままでなんとかやってきたが,かかわりがたいへんで……」ということは聞いてはいたのですが,私はあまり情報もなくAさんのもとに向かいました。
私:「Aさん,こんにちは」 Aさん:「……」 私:「よろしくお願いします(顔を見ようとする)」Aさん:「……(無言で反対のほうを向く」
こんなやりとりのくり返しで数日が経過しました。あまりにもかかわりが進展しないので,もう少し踏み込んでみようと思い,スタッフに「いまからAさんにかかわってくる。大きな声があがるかもしれないけど」と伝えAさんのところへ行きました。そして,あいさつと一緒に肩にポンとタッチ。案の定「イヤー!」と叫びながら部屋の隅のほうへ。でもあきらめずに「握手しましょう」「イヤー!」「ちょっとお顔を……」「イヤー!」「じゃ,何かお話でも」「イヤー! 変な人ー!」このくり返しをまた数日。ほかのスタッフは毎日Aさんの大声を聞かされ,「よくやるねえ」と半ばあきれ顔。
ある日Aさんから「なんで私のところに来るの?」と聞かれた私は「このままだと心配で,放っておけないから。なんか力になれないかなーって思って」と伝えました。すると「えー,私のためなのー」とAさん。それから少しずつ顔を出してくれ,入浴もできるようになり,治療にも協力してくれるようになりました。関係ができはじめたころは対応する看護師も限定的でしたが,治療が進むにつれ全員とかかわれるようになりました。主治医からも「よく打ち解けたね。治療できるようになったね」と言われました。
自分では特別なことをしたつもりはなかったのですが,あきらめない,相手に対してきちんと興味を示し,「あなたのために何かしたい」という姿勢を示したのが効果的だったのかもしれません。自分もこの事例を経験した後,自分のケアについて何気なくしていたことをきちんと考えながら技術として使えるような考えをもつようになりました。自分のケアを見つめることを教えてくれたAさんでした。
|
| |
(山形県・医療法人二本松会山形さくら町病院・佐藤大輔)
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |