|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
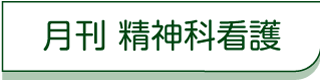 |
 |
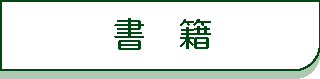 |
 |
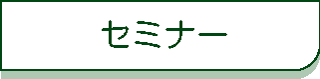 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第22話 「私はビールがいいですね」
|
| |
私は現在,高齢者を中心とした療養病棟に勤務しています。しかし閉鎖病棟なので,まれに精神症状が目立つ閉鎖病棟処遇の患者がベッドコントロールを理由に転入され,日常行っている看護とは違うはたらきかけやケアが必要となります。
昨年,アルコール依存症のAさん(60代男性)が,入院当初に離院したためARPを適応しないで,認知機能の精査を目的に転入されてきました。Aさんは失禁を認識できなかったので排泄は介助を要しましたが,そのほかは自立していて問題ありません。自宅へ帰りたい気持ちが強く,常に荷物をひとまとめにして「帰んないといけないんだよ!」「出口はどこ? いいから早く開けろ!」「できない奴だな!」などと荒い口調で,特に女性看護師を威嚇したり見下したりする態度を見せました。また「ちょっとウイスキー1杯くれない?」「なんでもいいから酒くれよ!」とアルコールへの欲求も強い状態でした。
外出許可のないことやアルコールの出せないことを看護師が説明しても,Aさんはイライラしたり,すぐに忘れて同じことをくり返し訴えたりしていました。病棟には精神症状の目立つ患者は少なく,日常生活上の世話や身体管理が主なので,私たち看護師もAさんの言動に怒りを覚えたりおびえたり,対応に苦慮していました。
あるとき,Aさんがいつものように「ウイスキーか何か,ないかな?」と言ってこられました。私は内心“またか……”と思いつつ,それまでとは態度を変えて「ウイスキーですか。今日は暑いから,私はビールがいいですね」と返すと,Aさんは「そうだろ? ちょっと何か飲まないとやってられないよ」と言われました。そこで「でも,ここでアルコールを飲まれたら,私がクビになっちゃいます。そしたら生活できなくなるので,出せないですよ」と続けました。「じゃあ俺が給料出してやるよ」とAさん。私が「でも安い給料じゃあ,やってられないなあ……」と言うと「いくらならいいんだ?」とAさんが聞いてくるので,「うーん,年俸3,000万円くらいじゃないと」と答えました。すると「それくらい軽いもんだよ。出せばいいんだろ?」とAさんは言うのです。「本当? でもAさん,いまお仕事してないし,私を個人的に雇えるんですか? なんか心配だな」というと,Aさんは「大丈夫だよ」とアルコールのことを忘れているようでした。そして「じゃあ,そういうことでよろしくお願いします」とまとめると「オウ」といって,Aさんは去っていきました。
何のことはない,飲酒の欲求におつきあいしながらも話をそらしたら,Aさんは一瞬アルコールを忘れ,イライラしなかったのです。
私たちは看護師という立場から,とかく禁止やルールの説明をしがちですが,会話のキャッチボールをすることで患者の欲求を転換したり,やわらげたりすることができるのだと感じました。そして,そうしたやりとりは同時に,私がAさんに感じていた怒りやおびえの感情をいくらか緩和させたのでした。
|
|
|
| |
第21話 「患者さんも私のことを見ている」
|
| |
数年前,私が急性期治療病棟に所属していたころにかかわったAさんの話です。
当時,病棟では老年期うつ病や認知症患者さんが多くを占めていました。入職1年目の私はそういった方の日常生活のケアに追われてしまい,ほかの患者さんとゆっくりとかかわる時間がもてませんでした。Aさんは私と同世代で,うつ病の治療のために入院されていました。いつも表情が冴えず,背中を丸めうつむき加減でした。Aさんは自分のことに精一杯であるにもかかわらず,隣室の認知症患者さんを気にかけてくれ,手を引いて食堂まで連れてきてくれたり,「おトイレみたいなんですけど……」と教えてくれたりしていました。
ある日,Aさんが「こちらのおばあさんが……」とナースステーションに来られたとき,私は「いつもありがとうございます。Aさん自身もつらいのに,やさしいですね……」と伝えました。するとAさんは「いつも見ていてくれたんですか?」と恥ずかしそうにされ「私も,矢田さんのこと見ていましたよ。いつもきちんとお化粧していて……。朝,忙しいでしょ? ……私も見習わなくちゃと思うんですけどね……」と話してくれました。
なんだかとてもうれしくなった反面,照れと驚きも感じました。患者さんも私のことを見ている。看護師として,そして同世代の女性として私のことを見ているのだと……。
その日以来,Aさんは「久しぶりに鏡を見た」とか「口紅をぬってみたんだけど……」と語ってくれるようになり,少しずつ女性らしさや自信を取り戻しているように感じられました。Aさんの化粧や表情は精神状態のバロメーターのようで,退院が近づくころには顔全体に薄くきれいな化粧ができるようになり,「矢田さんみたいにお化粧できるようになってうれしい」と話していました。
急性期治療病棟では社会生活に戻るというプロセスを看ることができます。私は看護師として,Aさんに何か特別なケアをしたというわけではありません。私にしてみたら化粧は何気ない日常的な行為だったのですが,Aさんにとっては,同世代の健康的な女性のモデリングになっていたのかもしれません。特に精神科看護では,私たち看護師の存在や振る舞いがケアの1つになり得ることを実感した体験であり,同時に,私はAさんから,自分の存在意義に気づかせてもらうことができました。
いまでも化粧をしながら時々,Aさんのことを思い出します。女性として,そして看護師として初心に返る瞬間であり,大切にしたい出来事です。
|
| |
|
|
第20話 あんたも見てたん
|
| |
昔,私が勤務していた病棟に,田中さん(仮名)という女性の老年期うつ病の患者さんが入院されてきました。入院当初は「なんかな,不安なんや。どうしたらいいか,わからんのよ」と訴えていた田中さんでしたが,徐々に「腰が痛いから立たれへん。手伝って」など,訴えの内容が変化してきました。やがて,あるスタッフからは「田中さん,1人のときは自分で立って歩いてるよ」という情報が寄せられました。その後のカンファレンスで「介助は安易に行わず,できるだけ見守りで」という方向性になりましたが,「手が痛いから布団かけて」「腰が痛いから座らして」と田中さんの訴えはエスカレートしていきました。私を含めたスタッフは,これがうつ病の身体症状の訴えだとは気づかず,その後も訴えはエスカレート。いつしかスタッフ側は陰性感情を抱いていきました。
当時,私は田中さんの受け持ちではなく,隣の部屋の担当で,かかわりはそれほどありませんでした。いつものように隣の部屋で業務を行っているとき,ふと窓の外を見ると,一羽のサギが屋根にとまり空を眺めている光景に出くわしました。「あんな鳥がここにおるんや」と思いつつ,何かホッとする感覚を覚えていました。それから数か月も経つと,そのサギは同じ時間に同じ場所にとまり,空を眺めているということがわかりました。
ある日,田中さんの担当スタッフから「会議があるから,ちょっと看ておいて」と言われ,私は部屋を訪れました。田中さんは椅子に座り,窓の外を眺めていました。ちょうど,あのサギが屋根にとまり空を眺めている時間でした。「あの鳥を知ってます? いつも来てるんですよ」と声をかけると,田中さんは小声で「知ってる。いつもここに来てとまってる」「あれ見てるとホッとするんよ」と話され,「あんたも見てたん」と目に涙を浮かべられました。田中さんは続けて「私,みんなに嫌われて一人ぼっちやから。さびしい。でも,同じ景色をあんたも見てたんや。うれしいわ」と,涙ながら微笑んでいました。その後,私たちは何も話さず,ただサギを見て時間を過ごしました。
田中さんには身寄りがなく,過度に身体症状を訴えていたのも,背景には絶えざる孤独があったのだと思います。そんな田中さんとひととき,景色と時間を共有し,心地よい空気感と,人が人として接することの大切さを感じました。教科書からは学びにくいことを,田中さんは私に教えてくださいました。最後になりましたが,田中さんのご冥福をお祈りします。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第19話 おばー,まぁかいやむんば?(おばあちゃん,どこが痛いの?)
|
|
私は高校卒業後,兵庫県の仁明会病院に就職しました。ある日,夜勤で出勤すると懐かしい言葉が耳に入ってきました。「えー,いったー,たぁええが? わんにぬーそうが(訳:あなたたちは誰? 私に何をしようとしているの?)」。これは,私が生まれ育った沖縄の方言。沖縄出身の認知症の患者様(Aさん)が入院してきたのでした。Aさんは沖縄から本土に出て来て50年になる方でしたが,家族の話では「最近は方言しかしゃべらなくて,怒ってばかりいるんです」とのことでした。
Aさんはケアのときも「あがー,あがー(訳:痛い,痛い)」と言われて,ケアを拒否されることもありました。スタッフは「あの人は何と言っているのだろう? さっぱりわからない」と困っていました。私はしばらくの間,ほかのスタッフと同様に,標準語または関西弁で話しかけていました。しかし,Aさんのスタッフに対する不安感,拒否的言動は消えず,認知症周辺症状はさらに激しくなりました。
その日の排泄介助の際も,Aさんは「やむんりば,やったーかしまさい,あまかいいけ(訳:痛いって,あなたたちしつこい,もうあっち行って)」といつものように怒っていました。そこで私は失礼にあたるとは思いましたが,あえて沖縄の方言で「おばー,まぁかいやむんば? めーなちわじて(訳:おばあちゃん,どこが痛いの? 毎日怒ってるけど)」と話しかけました。すると,Aさんの表情が変わり「やー,うちなーんちゅか? わじゃーちばりよ(訳:あなた沖縄の子? 仕事がんばってよ)」とこのとき初めて,Aさんのやさしげな笑顔を見ることができました。
そのときから,私は標準語より方言のほうが安心感を与えられるのではないかと思い,Aさんとスタッフの間で通訳がわりとなり接しました。そのうちスタッフもAさんに対して,方言を使ってケアやコミュニケーションのきっかけをつくるようになりました。会話の前に笑顔で「ちゅらかぁぎぃーのAさん(訳:美人なAさん)」と沖縄の方言を使って話しかけるのです。Aさんも「ぬーが(訳:何ですか?)」と笑顔で答えることが増え,「ここにも自分のことを理解してくれる人がたくさんいる」とスタッフに対して信頼感がもてたようでした。またケアにも,協力的に対応していただけるようになりました。
認知症で入院される患者様の多くは,なぜ入院しなければならないのか理解できていません。顔見知りのいない病院に入院することは,精神的に大きなストレスとなり,周辺症状の悪化につながることもあります。認知症の患者様に対して,個別の文化背景に配慮し,安心感のある環境を提供することが,いかに大切なケアであるかということを,Aさんは私にあらためて教えてくれました。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第18話 支援する問題じゃないとわかったから
|
|
Aさんに「訪問看護を利用して“あれがよかったなぁ”って思えた出来事はある?」と質問してみた。Aさんはしばらく考えた末「看護計画から『眠れない』という項目を外したことですよ。それで気が楽になりましたから」と笑顔で答えた。自分としてはそれまで「Aさんが思い描く理想の生活に近づけられるように」「人間関係が少しずつうまくいくように」「少しでも多く,少しでも遠くへ外出できるように」と意識して支援してきたつもりだったので,意外な答えだった。思わず「……ほかにはなかった?」と聞き返してしまった。
入職して初めて訪問看護の契約に立ち会ったのが,Aさんとの出会いだった。カーテンを締め切り,荷物がひしめく汗臭いワンルームでの,9年間の単身生活。クリニックへの通院以外は自宅にひきこもり,食事はファミレスのデリバリーサービス。以前は活動的だったというAさんが「いまの状況をどうにかしたい!」と担当医に相談したのが,訪問のきっかけであった。
訪問するにあたり立案した看護計画は“#1考えをうまく行動に移せない”“#2睡眠リズムが安定しない”の2つ。Aさんが「問題」とするものをあげ,体調や生活の変化を共有しながら,振り返る時間をもち訪問を続けた。Aさんも「生活リズムを整えたい」と,昼夜逆転しない薬を出してくれるよう,担当医に交渉した。薬が合わず,一時はより体調を崩すこともあったが,回復をあきらめることはなかった。Aさん自身,睡眠パターンの修正に熱心に取り組まれ,こちらも「睡眠時間の確認」「改善策の検討」する支援を続けたが,いっこうに睡眠リズムは整わなかった。
ある日,Aさんが「生活リズムの話はもういいので」と言われた。睡眠への意識やパターンについては,これまでAさんと確認しつづけてきた。かかわってきた経過を振り返ると,いまのAさんは生活リズムが改善しないながらも,眠るために自分で工夫をこらすなど,以前とは変化してきたこと,実際に行動する力がついてきたことも感じていた。そこで次月からは,#2の項目を消去した看護計画を提示した。Aさんは渡してすぐ気がつかれた。「こっち(看護師)は問題のように感じるけど,支援する問題じゃないとわかったから外したよ」と説明した。
Aさんの言葉で,利用者と一緒に作成して実施している看護計画であっても,看護師の力を借りずに「自分で解決したい問題点があるのだ」ということが確認できた。看護にとって大切なこと=人生の邪魔にならないように精一杯利用者の想いに添うこと,をあらためて思い返すことのできた出来事であった。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |