|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
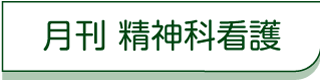 |
 |
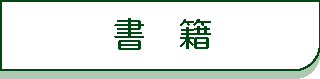 |
 |
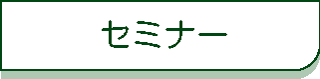 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第32話 「ゼリーくらいなら食べられる。口から食べたい」
|
| |
私の現在の看護スタイルを決めた,とある事例を紹介したいと思う。それは私が精神科看護をはじめてまだ間もないころのこと。
Vさんは70代の女性で統合失調症を患っていた。私が配属されたころは昼食だけではあったが,みずから食事を摂取できている状態だった。しかし時間が経つにつれ,次第に「口と胃がバラバラだ。何も食べられない。困った。死んだのと同じだ」と話しながら,みずから摂取することをやめてしまった。その事実を目の辺りにした私は,『なぜそんなことになってしまったのか? このままで本当にいいのだろうか……』と悩みはじめた。
そんな状態のまま,しばらく時間は経過していった。『このままではやはりいけない。何とかするべきなのでは?』と思った私は,まずVさんの24時間の生活パターンを観察することにした。すると,日中はずっと幻覚妄想状態にかられているが,夜間覚醒時には比較的自分の思いを表出し言語化できることがわかった。そこで,日中は信頼関係を築くために話を聴き,本人とつらいことを共有する。夜間は,本人が今後どのようにしていきたいのか,話を聴くように徹底することにした。また,私のほかにも賛同してくれるスタッフがいたので協力をしてもらうことにした。
こうしたかかわりをはじめて3,4か月が経過したある夜間帯のこと。その日,私は廊下で仕事をしているとVさんが私のそばにいすをもってきてそこに腰かけた。いつもどおり会話は「お腹がバラバラだから……」と始まるのだが,そのときは違った。
「あのね。私,口から何か食べてみたいと思うの。やっぱりこの管〔経鼻胃管〕ずっとはいやなの。何とかしたいとは思うけどどうしようもないのね。困った,困った……」と話したのである。昨日の日勤帯,Vさんにはいつもどおりに日中思いを受け止めると同時に,「またご飯食べられたらいいですね」と話をした後だった。私はうれしくなり,「そうね。ずっと管じゃいやだね。何が食べたいですか?」と聞くと「ゼリーくらいなら食べられる。口から食べたい」と話してくれた。そんなやりとりを一通り終えると,Vさんは「ありがとう」と話して自室に戻って休まれた。
先のやりとりを医師に報告し,だめもとでゼリーを提供することにした。当初Vさんはためらったが,次第にみずからスプーンをとって口にしはじめた。最初は2,3口。徐々に半分。そして1個と量が増えた。最終的に食事を提供するというレベルにはいたらなかったが,ゼリーだけは食べることができるようになった。しかし現在は,残念ながらVさんの病状が悪化し,経口での摂取をすることが難しく,経鼻胃管から経管栄養剤を注入して食事をするようになってしまったのだが……。
よく精神科では,夜間寝ないと病状が悪化するからすぐに寝なければいけないという。それも大切なことではある。しかし,必ずしもそれだけでよいのだろうか? その人が思いを表出する時間をもっと大切にするべきなのではないかと私は思っている。こころに寄り添う時間,それが大事だと思うのである。
(宮城県仙台市・IMSグループ 医療法人明理会西仙台病院・成田真人)
|
|
|
| |
第31話 「いままでの人生で,いちばんうれしかったことはなんですか?」
|
| |
在宅で生活する,歯肉がんと診断された80代の男性Aさんの話。
数年前に歯肉の痛みを訴え,ある病院の外来で「歯肉炎」だと言われ,ひとまず在宅で様子を見ていた。数か月後,疼痛が激痛に変わり,末期がんと診断された。「最初の段階で適切に処置できていたら,こんな人生ではなかったのに。最悪の人生になってしまった。あの医者は許せない」。
私が初めて訪問した時にも,その話を1時間ほどされ,不満や恨みで心がいっぱいになっているのが見てとれた。「人生を肯定的にとらえる」など,とてもできる状態ではないように思えた。私や訪問医には「ありがとう」と言ってくれるが,話題は決まって医療者への不満の話。家族ともよくその話になるらしい。
そこで私は足浴とタッチケアという,不安を取り除くケアを中心に行うこととした。訪問日には,必ずどちらかを行い「私はあなたの味方です。何かあったら何でも言ってください。全力でサポートします」と伝えた。その後,何度か連絡が入るたび,すぐに駆けつけて対応し,安心してもらえるようにかかわっていった。
そのうちに少しずつ,医療ミス以外の話もしてくれるようになった。ある日,私はこう切り出してみた。「いままでの人生で,いちばんうれしかったことはなんですか?」。Aさんは「子どもが生まれた時かな,あの時はうれしかった,わしもまだ若かったしな。下の子の時は病院に行ったのだっけな」と笑顔で語ってくれた。
「わしが子どものころはこのあたりの川でよく遊んだもんだよ。そうだ,先生は浪曲を知っとるかい?」「知りません」「知らんのか? 先生はいろいろ知ってるけど,浪曲を知らんのならまだまだやなあ」。Aさんは浪曲で賞をもらったことや,奥さんとの出会いも話してくれた。その日は,医療者への不満の話は一度も出なかった。
その後のAさんの表情は,とてもよくなっていった。関係性ができてくると,Aさんから「孫に会いたい」「孫に会えるその日まで何とか生きたい」という希望が出るようになった。しばらくして,孫にも無事に会うことができた。
その後の訪問でAさんはこんなことを話した。「もう孫にも会えたから,いつ亡くなってもいい。あんまり長い間生きると家族にも迷惑がかかるしな。できるなら苦しまないほうが助かるな。点滴は明日で最後でええわ。80歳を超えるまで生きられて幸せやったわ。先生に出会えて本当に感謝しとる。ありがとう」。とても充実した表情だった。Aさんは,その数日後に亡くなった。人生のストーリーを肯定的に意味づけをすることは大切だ。ただ,そのためには,人に寄り添い,関係性をつくり,思いを言葉にしてもらい,それを傾聴し対応していく必要がある。あたりまえのことだが,それを真摯にできるかどうかでケアは変わる。誰の人生にも,「うれしかったこと」がある。時に,それが見えなくなってしまう。うれしかったことを語ってもらうことで,良い人生だったと思ってもらえるように,ケアをするのが私たちの役割だと教えてくれたAさんに,いまは感謝でいっぱいだ。
(愛知県名古屋市・アープ訪問看護ステーション・藤野泰平)
|
| |
|
|
第30話 「いま,そこで,何が起きているのか」
|
| |
私が勤務していた病院での先輩看護師の体験談。新米看護師だった私が“看護”というものを深く考えるようになり,看護師の存在意義を探究するきっかけになった2つの物語である。
「ビル管理をしている」という妄想に苦しんでいる患者さんを受け持っていたA先輩。ある日,その患者さんから「管理しているビルが多くて疲れる。夜中でも急に起こされるし,そのことで食事もろくに喉をとおらん」と相談があった。そこでA先輩はこのように話したという。「よく頑張ってこられましたね。しかし体が資本! あなたが 壊れたら何にもなりませんから,相談してビルの管理を減らしてみましょうよ」。妄想を肯定したともとれる対応であるが,患者さんは翌日「Aさん,おかげで(ビルを)半分減らして仕事が楽になった」と話し,その後は健康状態が改善したという。1年後,私はその患者さんの受け持ちになったが,そのときに患者さんから元気な表情でそのエピソードを聞いたことをいまでも覚えている。
次はB先輩の話。ある女性患者さんは,毎晩のように幻聴に苦しみ「お母さんが“ごめんなさい,ごめんなさい”って言うの……」と泣きながら詰所に来ては話を聴いてもらっていた。看護師はやさしく話を聴き,落ち着くまで対応していたが,不安が和らぐことはなかった。
ある日,夜勤担当となったB先輩。深夜0時を回ったころに彼女が泣きながらやって来た。「お母さんが“ごめんなさい,ごめんなさい”って言うの……」。泣いている彼女にB先輩はこう話したという。「○○さんは,お母さんに謝りたいことがあるのかな。今度お母さんが来たら私も一緒にいるから,お母さんに気持ちを伝えてみようよ」。謝りたいのは彼女のほうだというのがB先輩の見解。数日後,その患者さんは面会に来た母親を見るなり号泣し,謝りだした。以後,お母さんの“ごめんなさい”という声はなくなり,その翌月に退院となった。私は数年後に外来で彼女とお母さんに会い,そのときの話を聞くことができた。彼女はあの面会以後,自宅で問題を起こしても人に謝ることができるようになり,パニックを起こさなくなったという。そして,その様子を語るお母さんのやわらかい表情からは,B先輩への感謝の気持ちがにじみ出ていたのを覚えている。
「妄想を否定も肯定もしない」という対応技術や,対象者の心の中で何が起きているのかを理解するための力動的な解釈などは,診療上の大切な技術である。しかし理論上の解釈は「いま,そこで,何が起きているのか」をていねいに取り扱ったうえで必要とされるものだと思う。先の2つの対応は,一般的には妥当とはいえないのかもしれない。ただ,患者が何を必要としているのかをていねいに取り扱う姿勢に“看護の独自の性質”があると感じている。看護師はなぜ必要とされるのか。それはさまざまな環境下で病気や障害という要素を抱える人の“安心感を回復させる”ことが私たちの最大の役割であり,独自性だからではないか。この物語を体験してから十数年が経ち,私の中でこの考えは推測から確信へと変わりつつある。そして現在,私にとって看護とは“価値ある生き方を教えてくれる大切なもの”となっている。
(山口県宇部市・山口大学大学院医学系研究科・草地仁史)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第29話 「“ターミナルケア”ってこんなものでいいの?」
|
|
渡部さん(仮名)は統合失調症の男性患者だった。妄想はあるものの目立った問題行動もないため,入院後間もなく他病棟へ移動。その後,眼球,皮膚に黄染があり,肝機能上昇がみられるようになった。黄疸も増強していったが,「俺は病気じゃない!」との妄想もあり,検査拒否,拒食や拒薬が続いた。胆管癌かすい臓癌の疑いがあることから,精神症状の治療と今後の治療方針を検討するために,私が勤務する病棟に戻ってこられた。しかし,依然とも拒絶状態は続き,チームで何度も検討した結果,ターミナルケアでのかかわりとなった。
渡部さんは人とのかかわりを好まれなかった。「私はどこも悪くないから測る必要もない!」と検温を断られることや,「具合はどうですか?」と尋ねても「何でそんなこと聞くんだ!? どこも悪くない!」と怒られる。そんな日々が続いた。
しかし,かかわりをもって何日か過ぎたころ,不意に採血をさせてくれることがあった。腫瘍マーカーは数値が測れないほど高く,入浴も拒否しているために全身状態の把握もできない状況だった。先のように治療の拒否は依然続いたが,とにかく渡部さんが孤立しないように通いつづけた。「いま,渡部さんにできることは何か」とチーム全体でひたすら考え,とにかくめげずに頻繁に足を運びコミュニケーションをとること,少しでも多く食事をとってもらえるように努めたが,目立った効果はない。「ここで作ったものには何か入っている! だから食べない」と話される渡部さんに,「なんでもいいです! 何か食べたいものはありませんか?好きなものは?」と尋ねると,「アイス,納豆巻き……」との答えが返ってきた。すぐに栄養科と相談,3度の食事のほかにメイバランスアイスを毎食,昼前に納豆巻きを2つお渡しすることにした(本人には売店から購入していると説明)。はじめは「おいしい」と食べられていたが,今度は「毎日納豆ばかりでは栄養が片寄ってしまう! そのあたりもよく考えてくれよな!」と話された。かんぴょう巻き,きゅうり巻き,おいなりさんと品を変えるものの,時に「味が薄い!」「酢が足りない!」「漬物がない!」と,ゴミ箱に捨てられてしまうこともあった……。
一方で,渡部さんの心境には徐々に変化もみられはじめていた。ときどき検温をさせてくれるようになったり,みずから話しかけてきたり,ときには笑顔も見られた。しかし,それに反比例するかのように,全身状態はしだいに悪化。ある日の夜勤明けに姿を見かけたのが最後。その翌日の朝に亡くなられた。
お見送りのときの顔は穏やかなよい表情で,私はどこかほっとしていた。しかし,「つらい」「苦しい」「痛い」といった言葉は聴かれなかったけれど,本当は相当つらかったと思うし,自分の病気を自覚していただろう。「“ターミナルケア”ってこんなものでいいの? もっとほかにできることがあったんじゃない?」といまも思う。ただ,何もかもを拒絶し孤独に生きてこられた渡部さんに少しずつ心境の変化があったことを,私はいまもうれしく思っている。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第28話 「山田じゃない!!」
|
| |
「山田じゃない!!」「直す,直すっていつになっても同じじゃない!」。穏やかに過ごしていた山田さん(仮名)が昼食の食札を見て一変,著明な興奮状態となった。この出来事は入院から1週間後のこと,終日隔離から開放観察を開始した初日のことだった。これにより開放観察は中断。いまにして思えば,私を含めた援助者がその「名前」に対する妄想にていねいに対応していれば回避できた事態である。
山田さんは60代の女性。近くに住む息子さんの支援のもと一人暮らしをされていた。傘や未開封のペットボトル,買い込んだものの手つかずのままだった弁当を,暮らしていた団地の窓から外に投げ捨てるといった行動をくり返し,訪問した警察官にも噛みついて入院となったのだった。私が山田さんと初めてお会いしたのは入院翌日の日中,隔離室内で拘束され,持続点滴にて薬物療法が行われている状況だった。「死んだ人がそこにいる!」「山田じゃない!!」など,幻覚妄想と思われる話や食後に顔のかゆみを感じて「何か入れてんじゃないの!?」と被毒妄想と思われる話をしていた。
私は行動制限を解除するためのかかわりと並行し,生活状況をくわしくアセスメントする必要性を感じた。「山田じゃない!!」という名前の拒否の背景には,これまでの生活状況や人生が深くかかわっているように思えたからだ。そこで,短時間のかかわりを頻回に行うことを心がけながら,これまでのこと,そしていまの状況をどう感じているのか,山田さんに直接確認することを重ねた。結果,しだいに,ライフラインがすべて停止した環境の中で1人で暮らしていたこと,怠薬や障害年金受給の拒否があったこと,そして夫との死別の後に発症したことなどが聞かれるようになった。「もしかして,(薬袋に)『山田』と書いてあったから薬を飲まなくなった?」と尋ねると,静かにうなずいた。ライフラインの停止も,やはり請求書に書かれた「山田」という名前が関係していたのだそうだ。
回復するにつれ,山田さんはみずからの生い立ちについては懐かしむようにいろいろと話すようにはなったが,結婚後の生活については「いいから……」と話したがらず,いつもはぐらかされた。期限つきのかかわりであったために,残念ながらかかわりもそこまでとなってしまった。山田さんの発症の原因が夫との死別に直接関係していたのか,結婚生活はどうたったのか,本当のところはわからない。しかし,「山田」という結婚後の姓のかたくなな拒否からは,死別を受け入れられないがゆえに結婚生活を思い出すことをも拒否するような,強い“何か”がたしかにそこにあったように思う。
山田さんの入院に至った経緯や「名前」の拒否を,ただ「奇行」や「妄想」と片づけることはできない。精神科に従事する者ならば,その背景にある“何か”に至ろうとしなければ,必要な支援にはたどり着かないと思う。私は駆け出しの病棟管理者ではあるが,行動などの背景まで含めたアセスメントができ,ていねいなケアができる看護師を育てていきたいと考えている。ポイントはやはり「意味不明」とか「理解困難」などの言葉で片づけないことだろう。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |