|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
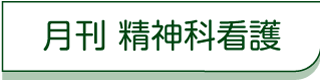 |
 |
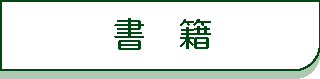 |
 |
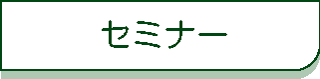 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第12話 「ええことが起こるで」
|
| |
私が新卒で就職した女子閉鎖病棟に,20年近く入院している統合失調症のAさんがいました。Aさんは自室の畳の上(当時は和室の病室)はもちろん,廊下やコンクリートの通路,テーブルの上や長イスなど,いろいろな場所ででんぐり返しをしていました。でんぐり返しをした後は,いつもその場所で体育座りをし,独語や空笑,時には大きな声で怒っていました。先輩の看護師はそのAさんの行動に対して,「Aさん,またでんぐり返りしたの? 痛いであかんよぉ」「危ないから,したらいかんよ」とAさんに声をかけ,後頭部の観察をしていました。私もAさんに対して先輩と同じかかわりをしていました。
あるとき,Aさんがいつものように前転をし,じっと体育座りをしながらうれしそうに独語をしている姿がありました。怒りながら,独語をしていることが多いAさんが,このときはニコニコと空笑しながら小声で独語をしていました。怒っているときに声をかけてもあまり返事をしてくれないAさんですが,そのうれしそうな表情を見て,ふと「何がうれしいのかな」と思い,体育座りをしているAさんの横にしゃがみながら「Aさん,どうしてでんぐり返りしてるんですか? いまはうれしそうにしとるけど」と,思ったことをそのまま話しかけてみました。するとAさんは「ええことが起こるで」と話されました。「でんぐり返りするといいことがあるんですか?」ともう一度聞いてみると,「うん。ええことが起こるん」と答えてくれました。
Aさんにとってでんぐり返りは「よいことが起こってほしい」という思いからの行動だったのです。でんぐり返りの後に何もよいことがないとわかったときに怒り,よい幻聴が聞こえているときには笑っているというAさんの素直な感情を表現した意味のある行動でした。そんな意味のある大切な行動とは知らず,「したらいかん。危ないから」と,でんぐり返りをしようと準備しているAさんを止める看護師に対して,Aさんが怒るのは当然のことでした。私は「患者の行動の意味を理解する」という大切な看護をAさんから教えてもらったと思っています。
私は以前,看護専門学校で専任教員をしており,「統合失調症の患者の行動には意味がある」という内容の講義をするときには,このAさんのでんぐり返りの話を学生にしていました。患者の行動には意味があると理解していても,それを実感する機会が少ない学生にとって,この話はとてもわかりやすいもののようでした。さらに学生には統合失調症の患者の行動を理解することはとても難しいけれど,その行動の意味を理解するために感受性を高めてほしいと伝えてきました。
医療や看護の理論は日々進歩し,その新しい知識を得て精神科看護に活かそうと自己研鑽を重ねることが重要ですが,この患者の行動に何気なく興味をもつことができた新卒時代の貴重な経験が,いまの私の看護の基本となっています。
|
|
|
| |
|
| |
ある患者さんの退院を想定しての会議で,病院の先生は「病院ではS子さんに食事も水分も一口も与えることができず,毎日点滴を1,000ccしている。レビー小体を発見したが,薬は体質に合わず危険があり,中止して以前の薬のみにした。入院3か月になることと,病院でできることはもうない。飲食はあなた方ならできるかもしれない」。私は先生の話に噛みつき「入院前は無呼吸が激しいことと,飲食の拒絶と幻覚がひどいので入院をお願いしました。症状も飲食も同じ状態なら,一度,栄養改善のために胃ろうはいかがでしょうか」と懇願。先生は「あなたたちならできる。悪くなれば入院を受ける」。そこまで言われれば腹をくくるしかない! 「何日見られるか不安だが,やってみます」。こうして2日後の退院が予定された。看護と介護のスタッフたちは,どんな反応をするだろうかと不安をもちながら私は会議を招集した。
「先生は,『病院は限界だが私たちにならできる』と信じて退院を決めた。アルツハイマーではなくレビー小体と診断された。治療も変わりない。まず栄養だけど,食事も水分も時間に関係なく1日の中でトータルで考える。つまり,『3食のご飯』と考えず,食べなければ栄養剤や補助食品やバナナやりんごのすりおろしなどを食べてもらう。水分もいろいろな保水液や冷水,カフェオレなどで工夫してみる。量的には,カロリーは800キロ以上,水分は1,200cc以上。かかわり方としては,決して無理強いをしない。“いまはだめだ”と感じたら仲間に代わる。タイミングを考える。場面を変える。楽しい話題を心がける」。看護師とヘルパーたちは大きくうなずき,口々にこう話した。「やってみましょう。先生に期待されたんだから,できるだけやってみましょう」。案ずるより生むが安し!
退院後,計画を実行。あるとき,嫌がるS子さんに無理強いをしているスタッフがいた。「仕事に忠実になり過ぎるのはやめよう。無理をすると嫌な気持ちになり,砂を食べさせられる気持ちになるかもよ。そのときは,方法を変えよう」。一定の食事が摂れてふっくらしてきたS子さんに笑顔が戻り,会話が通いあうようになった。ご家族は大喜びで「信じられない! 生き返ってくれた!」と以前と同じく車椅子に乗せて,風のような速さで遠方まで散歩に行かれる。ご家族の喜びは私たちの喜びと重なり連帯感となる。
2か月後,病院の先生に向けて経過報告と感謝の気持ちを手紙にした。「私たちにケアの工夫をする機会を与えてくださり,ありがとうございます」。
S子さんは,9月にははじめてのグランマになる。「こんな痩せ腕では孫が抱けないよ。リハビリもしましょうね」「そうなの? そうね」。咀嚼しながら笑うS子さんの周囲には,温かい空気が流れる。何が功を奏して改善されたのか不思議さは残るが,チーム力のすごさと,心により添える看護をまた1つ,S子さんから学んだ。
(東京都・多摩たんぽぽ介護サービスセンター・千葉信子)
|
| |
|
|
|
| |
「ここはあなたの来るところではありません。精神科の方はそっちに行ってください」。医師の声とドアが乱暴に閉まる音を聞くと同時に,私は待合室へと駆け出していた。少女が怒りを露わにし,物を投げたり蹴ったりしていた。頭痛がひどく受診したのに,「精神科に通っている」と話した途端,医師の態度が変わった理不尽さを,大声で訴えていた。あまりの勢いに,周囲の患者さんはもちろん,受付の職員も立ちすくんでいる。「こんにちは。私は外来の看護師です。一緒にいていいですか。落ち着いたらお話を聞かせてください……」。私は彼女に椅子を勧め,断ったうえで隣に座った。
彼女の思いや不安を聞き,受けとめたうえで,「主治医に相談をし,他科への受診が必要だと判断されたなら,紹介状を持って受診していただきたい」こと,「それなら今回のような対応はされないであろう」ことを伝えた。彼女は納得し,帰宅の手段を相談してきた。彼女の思いを尊重し,親でなく闘病仲間にお迎えを依頼し,無事見送ることができた。大学病院の精神科病棟に勤務した後,夫の転勤に同行。再就職した東京の救急病院での一場面である。
人の心を動かすのは,時に正論や理論ではなく,患者さん自身が「自分が大切にされた」と実感できることなのではないかと思う。医師の心ない言葉で傷ついた少女の思いをただ受けとめることしかできなかった私だが,あのときの医師の一見理路整然とした言い分と少女の涙は,私を精神科の現場に戻らせたターニングポイントとなった。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2か月ほど前の話です。漠然とした不安があり他者とのつながりを強く求める患者さんがいました(以下,Aさん)。朝食を配膳するため部屋に入ると大きな声で「不思議の国のアリスが襲ってくる」「足が大きくなる」と興奮しながら訴えました。「急にどうしたの?」と話を聞くと「昔,読んでもらった不思議の国のアリスを思い出して……すごく怖かった」と話されました。しばらく付き添い,少し落ち着いたところで「ほかに読んでもらった本は?」と聞くと「ピーターパン……ピーターパンが好き」「『イッツアスモールワールド』も好き」と話されました。「じゃあピーターパンを思い出しながら『イッツアスモールワールド』を歌ってみようか」と提案し,部屋で一緒に熱唱しました。
歌いながら「アリスあっち行けって言ってみようか」と誘い,何度も一緒に「アリスあっち行け!」と言っているうちに,Aさんの表情は笑顔になっていきました。
その後,Aさんは入院治療の経過,順調に回復していきました。つい最近,Aさんから「あのとき,『アリスあっち行け』って言ってくれて助かったわ」と言われました。このときに,あの対応は「それなりに効果があったんだ」と感じました。何の根拠もないのですが,結果的にAさんが「助かった」と感じたことは事実です。臨床の現場で本人の好きなものに注目し,恐怖心を何か楽しい気分へ変換させられたら,と工夫した事例でした。
(奈良県・財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん・小瀬古伸幸)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8話 私は違う話がしたい
|
| |
10代の彼女は,極端なまでに自己評価が低い摂食障害患者だった。毎日,顔を合わせるたびに「私のこと,好き? 嫌い? ……嫌いでしょう」と泣き叫んでいた。0か100か。白か黒か。そんな思考や自己評価の低さは彼女に限ったことではなかったが,彼女は強烈だった。質問責めは24時間といっても過言ではないほどで,かかわりをもつスタッフ全員がうんざりして陰性感情を抱き,対応が困難であった。
あまりのしつこさに感情的な対処をしたベテラン看護師は「自分が信じられない」と自責の思いでいっぱいになっていた。それを聞いた私は「自分がしていたかもしれない」と思った。
その日から私は,質問に返答するだけの対応をやめた。好き嫌いを聞かれても返答せず,趣味や興味のあることを聞き返した。「私は違う話がしたい」「あなたのことを知りたい」とアイメッセージを付け加えて,根気強く話題の変換をしたところ,彼女の発言に幅ができ,体重増加や摂食への不安の会話ができるようになった。その後は自己評価の低さを話題に出せるようになった。もちろん楽しく趣味の話や,学校の話も継続した。
同じ訴えをくり返すのは,期待した返答が得られていない不全感があるものだが,彼女の場合は安心感を求めることだけが行動の理由ではないと感じ,とらわれから引き離す必要があると私は考えた。
患者の期待に沿う反応を示すだけでなく,患者のことを「知りたい」と思う気持ちが届けば,突破口はみつかるのではないだろうか。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |