|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
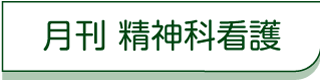 |
 |
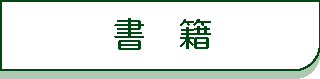 |
 |
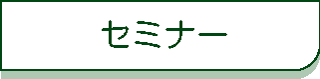 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第27話 「あなたも,私たちも苦しいね」
|
| |
50代の双極性障害の男性患者さん(Aさん)が,躁状態で入院してきました。しばらくして他患者とのトラブルと迷惑行為で隔離室に入室,抗精神病薬入り点滴が開始されました。
リピーターであるAさんは病状悪化すると病棟科長である私を指名して無理な要求をくり返し,「それをなんとかするのがあんたの仕事だろうが!」と怒鳴る日々が続いていました。点滴開始から3日目,この日の受け持ち看護師は私でした。4名ほどで入室し固定の最中に突然,彼の右膝が私の脇腹にガツンと入り,一瞬,痛みでうずくまりました。「縛られる俺の気持ちが,お前にわかるか! 俺にただで点滴できると思うなよ!」という怒声を耳にしてたまらなくなった私は,いったん退室して気持ちを立て直したものの,退室時に思わず仁王立ちで「Aさん,いま苦しい気持ちはわかる。けど暴力はいけない。スタッフにこんな痛い思いさせたら,私許さないから!」と叫んでしまいました。この日は(この人がいま,いちばん苦しいんだ)と何度も自分に言い聞かせ,受け持ちとしてかかわりました。
Aさんに対する陰性感情を抑えられなくなってきた私は,カルテ情報と記憶から彼の過去をたどりました。Aさんは有名大学を出て一流企業で商品開発に携わり,リーダーとしてチームを引っ張っていました。しかし病気により,解雇や離婚を経験されています。彼の,スタッフや私に向けられる激しい怒りは,本当は病気に対しての怒りではないのか。そう思うと,彼に寄り添えず憎しみや苦しみを受けとめられなかったばかりか,仁王立ちで説教をしていた自分がとても恥ずかしくなりました。
2日後,徐々に怒声が減りつつあるAさんは,訪室した私に「テンションが下がってうつになってしまうから,点滴は受けない。劇薬が入る前は生きる意欲に満ちてたからな~」とふらつきながら足蹴りの格好をしてみせました。私は思い切って聞いてみました。「私の脇腹を蹴ったこと,覚えてますか?」するとAさんは「……覚えてるよ」と,格子の間からそっと手を伸ばして,私の脇腹を擦ってくれました。いま,Aさんは「うつになりそうだ」と不安を感じている。私は「数日前より気持ちが通じあってよくなっている」と感じている。「躁とうつのバランスが保ちにくい病気だから,あなたも,私たちも苦しいね」と話しているうちに,涙が溢れてきました。Aさんは「俺はラピットサイクラーだからなぁ。あんた泣くなよ,もらい泣きするよ……」と言ってくださいました。
3週間後の退院前日,夜勤明けでAさんのところへごあいさつに伺うと「いろいろとありがとう。気をつけて帰ってね」と小さく頭を下げられました。静かな眼差しと右肩下がりの背広姿は,A氏の真の姿でないような気がして,哀しい気持ちになりました。今後,また病状悪化し再入院となれば,Aさんは私を罵倒すると思います。でも今回,Aさんと私の間で何かが変わりました。Aさんの中から病気という存在を切り離し,2人で同じ思いで眺める貴重な時間を共有できたからだと思っています。
|
|
|
| |
第26話 「身が引き裂かれる思いよなぁ」
|
| |
私が勤務している病棟のA氏は,入院期間が2年を超えようとしている。普段の彼は決して口数が多いほうではなく,物静かである。しかし退院の気持ちを聞いてみると「それは1日も早く帰りたいですよ。僕には家もありますから,先生にいつ退院させてもらえるのかを待っているんですよ」と堰を切ったように話しはじめ,いまだ退院できないもどかしさと先が見えない不安を打ち明けていた。
A氏はちらりと病室を覗いては,外出や外泊で他の患者様のベッドが空いているのを見つけると一目散に看護師に駆け寄って来て「ここにいた人はどこに行ったん?」「もしかして,退院したんかな?」と聞いてくる。そして,退院ではないと知るとほっとしたのかひとことの礼を言って去って行く。時には退院が決まり荷物をまとめている患者様にも声をかけ「ええなぁ。あんた家に帰れるんかな。すぐに退院できたんやなぁ。わしはまだ外泊しかできんのぜ」と愚痴をこぼしながら,うらやましさも隠さない。
これまでA氏は,自分よりも後に入院して先に退院していく人を何人も見送ってきた。そのたびに「元気でな」とはなむけの言葉を送りつづけながらも,みずからは無力感に覆われていたに違いない。いつだったか,仲間の退院を見送る側の心情を聞いてみたところ「それはそれはつらいよ。身が引き裂かれる思いよなぁ」という自然に出た言葉がすべてを物語っていた。看護師として,患者様にとっての退院の意味は理解しているつもりだった。しかし退院が飛び交う社会復帰病棟の中では思わずその意識が薄まってしまう瞬間があることを見透かされているようで,私はみずからを戒めた。
「なんで退院させてもらえんのかなぁ。薬を飲まなくなって衝動買いしただけなのに……家族も先生も厳しいわい」と話すA氏に「退院の許可を待っているだけじゃなくて,自分の気持ちを先生に言わなくちゃ」と伝えると「でも,そんなことを言ったら先生に怒られそうで怖いわい……家族も先生に任せるって言ってるし」と初めて主治医に対する思いを知ることができた。退院をめぐっては,患者様の希望と家族の不安に温度差が生じることが少なくない。A氏の家族も退院後の単身生活を心配されており,アウトリーチの導入を希望されている。「Aさん,退院したら,家に遊びに行ってもいいですか? 訪問看護のスタッフやヘルパーさんにも来てもらって,おいしい料理をつくってもらいましょうよ」「僕はまだ年寄じゃないからヘルパーさんなんていらないよ」「いや,一度は来てもらわないとわかりませんよ」,こんな綱引きをしながら,先日は「たまになら,デイケアにも行ってみようかな」という話が出て,少しずつ,退院への道を歩んでいる。まだ診察室で「退院したい」と言う勇気が出ないが,いまはA氏がタイミングよく退院の決意表明を出してくれることを待ちつづけている。
そして,もちろんA氏の退院の日にはみんなで「お元気で」とはなむけの言葉を送って大きく手を振りたい。だってA氏はその言葉をずっと待っているのだから。
|
| |
|
|
第25話 「同じように言われたらどんな気持ちになる?」
|
| |
精神科に特化した訪問看護ステーションに勤務して,2年が経とうとしています。「訪問看護が続けられるよう,利用者に拒絶されないように暮らしを支援することに,病棟とは違う難しさがある」とは所長のお言葉。利用者が自分で日常生活のさまざまな問題を乗り越えられるように日々,激励していますが,中にはかかわりの難しい利用者さんもいて,時には厳しい言葉が飛び交うこともあります。
一人暮らしのSさんは疾患に関連して被害妄想があり,不安や不信感が強く,他人とのかかわりを避けようとする傾向があります。生活支援としての掃除の際なども,自分は扇風機の前に座ったまま「掃除機はもっとていねいに扱ってや!」「トイレの掃除もしてな! 水を流すのは2回までやで!」と攻撃的な口調。一緒にかかわることが目標なので「Sさん,一緒にせぇへん?」と促がしても「しんどいねん!」。その横柄な態度や口調に,こちらも感情的になってしまうこともしばしば……。でもSさんは自分の思い通りにならないと不機嫌になり,プイと顔を背けてしまいます。どうかかわればよいのか,と悩みながら,それでも“Sさんの生活環境を少しでもよくしたい”という気持ちで訪問を続けていました。
その日も,Sさんは掃除をしている私に「掃除機,そんなに荒く扱わんといて! 壊れたら弁償してくれんの?」といつも通りの口調で向かってきました。私はSさんと向きあい,「その言い方はよくないんちゃう? 私も人間やから,そんな言い方されたら頭にくるわ! Sさんが同じように言われたらどんな気持ちになる?」と気持ちをぶつけました。するとSさんはしばらく私をにらんだ後に「じゃあ,どう言ったらよかったわけ?」と尋ねてきます。私は相手を思いやる気持ちをもってもらいたいと,気分を害さない言葉遣いや感謝の気持ちを表す具体的な言い方を提案すると「ふ~ん,うん,うん」と耳を傾けてくれて,理解しようとしている表情がうかがえました。自分の気持ちをぶつけたときはドキドキでしたが,Sさんのこの反応に救われたような気がします。帰り際に「今日は言いすぎたかもしれない,ごめん。これからもよろしくね」と握手を求めると,Sさんは「ああ,こちらこそごめん」と驚いた表情で受けてくれ,2人で大笑いしました。その後は「悪いけど,○○してほしいねんけど……」「助かったわ,ありがとう」といった言葉も聞かれ,Sさんの素直な性格も見えるようになりました。そして,支援に自発的にかかわろうとする場面が徐々に増えてきました。
Sさんと向きあったことで,相手をどんな気持ちにさせてしまうのかは,表情や口調も大きな要素になること,そして自分が変われば相手も変わる(悪いことも含めて)ことを学びました。精神科の訪問看護では,一般常識や地域生活上の対人関係などに対しても,利用者の方にアドバイスしなければならないことがあります。未熟な私ですが,広い視野と知識をもち,今後も利用者と一緒に,それらの問題を援助できるようにかかわっていきたいと思います。
(大阪府・ハントン訪問看護ステーション・前川勝美)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第24話 「は・ひ・ふ・へ・ほ」
|
|
「ねえねえ,私には宇宙人の恋人がいるのよ」「はっ,なんですって?」「18万光年彼方の宇宙から,迎えに来てくれるの」「ひょえー,宇宙から?」「宇宙で結婚式するの。宇宙結婚式」「ふーん,宇宙結婚式ですかぁ」「そうなの。彼は銀河鉄道に乗って来るの」「へぇー! 銀河鉄道で!?」「うん,もう切符も買ってあるんだって」「ほ,ほんとうですか!?」
妄想発言のある患者さんとのやりとりです。一見,いい加減にあしらっているように見えるかもしれませんが,これがけっこう効果的。妄想のある患者さんとの会話のコツ,それが当院自慢の「は・ひ・ふ・へ・ほ」です。
われわれにしてみれば突拍子のない,現実感に欠ける妄想発言。でも,患者さんにとってはまぎれもない現実。真剣に訴えてきます。そんな患者さんへの対応に苦慮していた数年前のある日,看護実習生の質問に答えていた当院の病院長の言葉に度肝を抜かれました。「あのね,妄想のある患者さんとの会話のコツはね,は・ひ・ふ・へ・ほ,なんだよ。何を言われても,は~,ひー! ふ~ん,へー! ほ~! たいていのことは,この5文字のリアクションでOK!」。僕はそのあまりに斬新(?)な考え方にびっくり。学生と一緒に驚きました。
妄想発言のある患者さんとのコミュニケーションの基本といえば「否定も肯定もしない」がセオリー。でも,その真意を知っている看護者は意外と少ないかもしれません。
「訂正不能の誤った確信」,そんなふうに定義づけられる妄想も,患者さんにとってはその人の“いま”を支えている大事な現実に他ならないことがあります。満たされない欲求やストレスを昇華させるために,妄想というもう1つの現実世界に身を置いてやっとの思いで自我を保つ。そんな患者さんも珍しくありません。
妄想は病気にもとづく症状なのだから,なければないほうがいいに決まっています。でも,患者さんの中にはその妄想に支えられて生きている人もいる。それもまた理解してあげたい。「は・ひ・ふ・へ・ほ」はそんな患者さんへの対応の基本。まずは否定せず,かといって肯定するのでもなく,受容と共感の態度を全身で表わす。それを教えてくださったのが院長先生だったのです。以来,実習指導者となったいまでも「妄想のある患者さんへの対応」の指導として,この「は・ひ・ふ・へ・ほ」のリアクションとその意義を必ず話すようになりました。
翌日,再びこの患者さんがやって来ました。
「ねえねえ,結婚式,やっぱり一億五千万年後に延期したんだ」「ひょっえー! 一億五千万年後?」「うん(笑)」
本当に……たいていのことはこの5文字でやんわり対応ができてしまうから不思議です。
(愛知県・桶狭間病院藤田こころケアセンター・鈴木信哉)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第23話 「オレ,海を見たの,初めてや」
|
|
発達障害のある15歳のA君は看護師に勧められ,海への散歩に参加した。気乗りしない様子でうつむきながら,黙々と歩いていた。海辺に着いたとき,彼は真剣な顔でじっと海を見て立ち尽くし「オレ,海を見たの,初めてや」とつぶやいた。「テレビで見て,海くらい知っとるわ。でも,なんやこれ」と,感動よりは違和感のあるような,複雑な表情に見えた。
三重県は海に面しており,A君の自宅から海までは,車で30分ほど。この地に生まれて,15歳になるまで海を見たことがなかったなんて,本当だろうか? と思い,A君に入院前の生活を聞いてみた。彼は「家には車もないし,毎日だいたい同じ生活やった。学校と,近くのスーパー以外は出かけん。電車に乗るような特別な用事は,ウザいで行かんようにしとった」と話した。彼は生活パターンの変化を好まず,幼いころから毎日,まったく同じライフスタイルで過ごしてきたのである。中学校に進学すると環境や対人関係の変化に適応できなくなり,不登校になった。言葉のやりとりも苦手で,自分の意を通そうと家族へ暴力を振るい,入院となった。どうやら本当に,海を見るのはこのときが初めてのようだった。彼は「新しいことは苦手やわ。変わらんほうが落ち着くんじゃ」とも話した。いままで外出しなかった理由を探して,自分を納得させているように感じられた。
発達障害のある児童はA君のように,障害の特性から変化を好まず,こだわりをもっていることも多い。対人関係や環境など,成長に伴うまわりの変化についていけず,思春期になると二次障害としての問題を抱えやすくなってしまう。体験が不足している児童も多いため,他者からの療育的な働きかけが重要となる。
この日を境に,看護師に促されながらも,自分の好まないことも含めて少しずつ新しいことに挑戦するA君の姿を見るようになった。体験を増すごとに自信をつけて,活発になり笑顔も多くみられるようになった。「頑固なこだわりがやわらいだ」と,家族もA君の変化を喜んだ。海を見たことが,A君の変化にどう影響したのかはわからない。しかしA君にとっては新しい,大きな体験であったことは事実であろう。
筆者の勤務する施設には約80名の小・中学生が入院していて,平日は隣接する分校へ通学している。週末は家族のもとへ外泊したり,病棟で余暇を過ごす。筆者は,入院してくる児童の生育歴を大切に扱いたいと考えている。入院までの数年間の歴史が,いまの彼らを映しだしている。彼らの話をじっくり聞いて1人1人の育った環境を知り,いままでの経験や考え,生活習慣などを理解できれば,個別ケアに役立てることができる。季節に応じた行事や活動計画を通して,欠けていた経験を補うこともできる。多くの児童に,自信につながる体験をさせてあげたい。児童精神科の看護師として,自分の役割を考える毎日である。
|
| |
(三重県・県立小児心療センターあすなろ学園・村上亜由実)
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
メンテナンスのため午前4:00~4:30 ショッピングカートは使用できません
Copyright (C) 2004 Psychiatric Mental Health Nursing Publishing Inc. All rights reserved. |